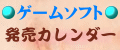Sidebar |
Rave レポートを ゼロからはじめてみよう[1]
設定をしてみましょう 1.Delphi側の設定 とりあえず。 DataSource1 Table1 RvProject1 RvDataSetConnection1 RvRenderPreview1 をフォームに配置します オブジェクトインスペクタで設定をします。 【DataSource1の設定】 DataSet : Table1 【Table1の設定】 DatabaseName : dbdemos TableName : country.db 【RvDataSetConnection1の設定】 DataSet : Table1 RvProject1を右クリックして、 Raveビジュアルデザイナを開きます。 保存でどこか保存します。 【RvProject1の設定】 ProjectFile : いま保存したファイル名を設定します ボタンを配置して。 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin RvProject1.Execute; end; とします。 2.Raveビジュアルデザイナ設定 (Reportウイザードを選択して、Simpleをクリックしていって、最後に保存でもいいです。 とりあえずなれるために 下の操作をしてみましょう) ReportタグからRegion1を選択していれます。 DataBand1をそのなかにいれます。 DataMemo1をそのなかにいれます。 新規作成DataObjectで、Direct DataViewを選びます。 右側のリストでDataView1を右クリックして、更新(Refresh)を選びます 項目が追加されたと思います。 DataMemo1をくりっくして。プロパティに代入します。 DataView : DataView1 DataField : Name Region1 DataView : DataView1 保存します。 3.Delphiに戻ります Delphiで実行します。 ボタンを押し プレビューを押すと 国の名前がでてきたと思います。 雰囲気はなんとなく つかめてきました。 続く・・・ Delphi2005についていたのは、 試していたら、 すぐには、PDF出力つかわないけど PDFの出力バグがあったので、なおるまで使えないな。 fillstyleかえるとPDFが読めない。 あと、 日本語を1バイトで折り返すので、 まともにレポートつくれないよぉ。 データ渡すときに 枠にはいるように こっちで改行してあげてないといけないっぽい。 面倒!! かなり料理してあげないと使えないなぁ ということで、 Rave レポートは、 おわり。 最悪、旧バージョンで データとレポート部分をQreportで処理して DLLで、操作するしかないな・・・ そうなると、Delphi2005を買った意味がない気がしてきた・・・{/face_z/} 次は .Net の Cristalレポートを使ってみるかな・・・ Cristalレポート9は斜線も引くことができない。 なんてソフトだ。 お話にならない (・_・ )ノ"" ゜ ポイッ うぁーーん Delphi2005買って損したよぉー 返品したいよぉー。 しくしく。 続く・・・ Raveの続きはこちら「2」 Delphi/Rave Report/はじめてみよう 「0」 「1」 「2」 「3」 「4」 リンク Rave Reports入門 Part I: Code Based Reports Part II: Visual Designer Part III: Data Aware Reports Part IV: More Data Aware Reports Delphi/IEをオートフィルしよう
サンプルコード function SetIE_AutoFill(vDoccument:Variant; ValueLists : TStrings ; vMode : integer ) : boolean; // vMode : 0 : ID, 1 : Name , そのた:ID var i : Integer; v_Items : Variant; vRet : boolean; begin vRet := False; Result := vRet; if VarIsClear(vDoccument) then exit; for i := 0 to ValueLists.Count-1 do begin case vMode of 1 : // 1 : Name v_Items := vDoccument.getElementsByName(ValueLists.Names[i]); else // そのた:ID v_Items := vDoccument.getElementById(ValueLists.Names[i]); end; // case vMode if VarIsClear(v_Items) then begin ShowMessage('v_Item null: '+ValueLists.Names[i]); Continue; end; // ShowMessage(v_Items.length); // 要素の長さ if (v_Items.length>=0) then begin v_Items.Item(0).innerText := ValueLists.ValueFromIndex[i]; vRet := True; end; end; Result := vRet; // v_Items := v.getElementById('ID'); // v_Items := v.getElementsByName('Name'); // v_Items := v.getElementsByTagName('body'); end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin // ListBox1.Items.Add('name'+ '=' + 'Value') SetIE_AutoFill(WebBrowser1.Document,ListBox1.Items,1); end; Rave Reportを ゼロからはじめてみよう[0]
設定をしてみましょう まず、ヘルプをざっと読んでみます。 ほんとに、全くしらないんで(^_^;) 緊張しますね・・・ しばらくお待ち下さい・・・ (リアルタイム・・・ ほんとにいま読んでます) <�2分経過> なんだか、一個のアプリケーションを操作するって感じ の雰囲気が漂ってきました。 <�3分経過> おぉ、バーコードも出力できるのですね。 すごいなぁ。 ついでにQRも出せるともっていいのになぁ <10分後> デザイナー起動 ぶーーーーーん ぶんぶんぶん。 あれ〜 よくわかんない。。。 とりあえず、何かつくってみよう Delphi2005起動、 ぶー〜ん? ぼこん ぼこん ぼこん」 ・・・ サンプルを試してみる・・・ ん? RAVファイルがないとつかえないのかぁ Q_Repoのほうがましかなぁ・・・ EXEと別につくるの面倒だし。 今日はおしまい。 とりあえず、DBと連携・・・ invalid ・・・ 効率わるいので使うのやめよう・・デザイナも使いにくいし。 Quickレポ今度のバージョンついてないし、しかたない 今度はCristal レポートに挑戦しよう DataView1を右クリックして更新を選んで保存をすると動きました Raveデザイナがバカだったんだぁ 続く・・・>> Delphi/Rave Report/はじめてみよう 「0」 「1」 「2」 「3」 「4」 リンク Rave Reports入門 Part I: Code Based Reports Part II: Visual Designer Part III: Data Aware Reports Part IV: More Data Aware Reports はじめてみようLinux
作成: 2005/04/04
編集:2017/02/19 Live イメージをダウンロードして、気に入ったらインストールするといいでしょう。 代表的なものに Linux Mint
があります2017/02 : (内容が古くなっていたため大部分を削除しました) Linux リンク
勝手にリンク Linux OS 高性能のOSです、タダなのがうれしい♪
サーバー向け
Linux 関連リンク/マルチメディア : Debian Live : CDのみで起動できるLinuxです。 ハードディスクを汚さずに試すことも ずっと使い続けることもできます。
Windowsが起動できないときの緊急用としてもいいかも LibreOffice : Microsoft Officeと高い互換性。 この性能で、無料なのがうれしい もう少し設定しやすくなったりして、
マルチメディア関係が、いまのWindowsレベルに到達すれば
OSシェアはかわるかもしれないな〜
Linuxで スクリーンショット
スクリーンショットソフト 一覧 KDE KSnapshot 場所: Kメニュー ⇒ グラフィックス ⇒ アプリケーションプラス ⇒ KSnapshot | Link GNOME スクリーンショット 場所: GNOMEメニュー ⇒ アプレット ⇒ ユーティリティ ⇒ スクリーンショット | Link X Window System import 場所:使いにくいので省略 | Link |
Sidebar |